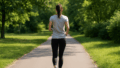にんじんを料理に使おうと切ったとき
「あれ?真ん中が白い!」と驚いた経験はありませんか?
鮮やかなオレンジ色を想像していたのに
中心が白くスカスカだと
「古いのかな?」「食べても大丈夫?」と
不安になりますよね。
実はこれは珍しいことではなく
にんじんの育ち方や保存方法によってよく起こる現象なんです。
この記事では
にんじんの真ん中が白くなる原因や
食べられるかどうかの見極め方
さらに美味しく食べる工夫やレシピまで
分かりやすく解説します。
家庭菜園で育てている方や
スーパーでにんじんをよく買う方にも
役立つ情報をまとめましたので
ぜひ最後まで読んでみてください。
にんじんの真ん中が白いのはなぜ?
成長過程で起きる中心部の空洞
にんじんを切ったとき
中心部分が白くスカスカしていることがあります。
これは主に成長の過程で起きる
「中心部の空洞化」が原因です。
にんじんは土の中でぐんぐん育つ野菜ですが
急激に成長すると内部の細胞が追いつかず
中心が空洞になることがあります。
その部分は見た目が白っぽく
しっかり詰まったオレンジ色とは違って見えるのです。
特に夏場や肥料が多すぎると成長が早まり
この現象が起こりやすくなります。
農家さんの間では
「す入り」と呼ばれることもあり
昔から知られている現象です。
見た目は少し驚きますが
この空洞は自然な成長の結果であり
食べても問題はありません。
ただし、空洞部分は繊維質が強く
食感が固く感じることがあります。
そのため、炒め物や煮物に使うときは
薄切りや小さめに切ると口当たりが良くなります。
このように、にんじんの中心が白いのは異常ではなく
成長のスピードに関係した
自然な現象だと覚えておくと安心です。
栄養や水分不足の影響
にんじんの中心が白くなるもうひとつの理由は
水分や栄養が足りなかった場合です。
にんじんは根の部分に栄養を蓄える野菜ですが
十分な水や栄養が届かないと中心部が十分に育たず
白っぽくなってしまうのです。
特に雨が少ない時期や水やりが不十分な畑で育ったにんじんは
この現象が起こりやすいといわれています。
また、肥料が不足している場合や逆に与えすぎた場合も
根の内部にバランスよく栄養が行き届かず
白っぽくなることがあります。
白い部分は栄養が少ないため
甘みが弱く、全体の味も少し淡泊に感じられることがあります。
ですが、それでも食べられるので安心してください。
もし甘みをしっかり感じたいなら
煮込み料理に使うと周りの旨みを吸って食べやすくなります。
にんじんの中心が白くなるのは
野菜の「育ち方の個性」と考えるとわかりやすいでしょう。
品種による違い
実は、にんじんの真ん中が白く見えるのは
品種の違いによる場合もあります。
にんじんには大きく分けて
「東洋系」と「西洋系」の品種があり
最近よく見かけるのは西洋系のオレンジ色が濃いタイプです。
しかし、東洋系や一部の固定種では
中心部分が薄い色合いをしていることがあります。
この場合、白っぽく見えるのは異常ではなく
その品種特有の特徴なのです。
特に家庭菜園で育てられる在来品種の中には
色が均一でないものも多く
「真ん中だけ少し白い」という姿になりやすいのです。
見た目は鮮やかさに欠けるかもしれませんが
味わいはしっかりしていて独特の香りを楽しめることもあります。
スーパーで売られているにんじんでも
輸入品や特定のブランド品では品種の影響が出ることがあります。
つまり、白さの原因が
「品種によるもの」ならまったく心配はいらず
むしろその個性を楽しむのがおすすめです。
保存状態が原因の場合
にんじんの中心が白くなるのは
保存の仕方が影響していることもあります。
にんじんは収穫後も呼吸をしており
時間が経つと水分や栄養が少しずつ失われていきます。
その結果、真ん中が乾燥して白っぽく見えることがあるのです。
特に冷蔵庫の中でそのまま保存すると
周りの冷気で水分が抜けやすくなり
中心部が硬く白くなりやすいといわれています。
これを防ぐには
新聞紙やキッチンペーパーで包み
さらにビニール袋に入れて
冷蔵庫の野菜室に保存するのが効果的です。
こうすると水分の蒸発を防ぎ
鮮やかな色を保ちやすくなります。
保存が長すぎると
どうしても中心が白くなることはありますが
それでも食べられます。
ただし、外側に黒ずみやぬめりが出ている場合は
鮮度が落ちているサインなので注意しましょう。
保存の工夫次第で
「白化現象」を防げることを覚えておくと便利です。
白くても食べられるのか?
多くの人が一番気になるのは
「白くなったにんじんは食べられるの?」
という点だと思います。
結論から言うと、中心が白いにんじんは
ほとんどの場合問題なく食べられます。
白くなる原因は
成長や保存の過程で起こる自然な変化で
病気や農薬の影響ではありません。
ただし、白い部分は
オレンジ色の部分よりも繊維質が多く
少し硬かったり甘みが弱かったりするので
料理方法を工夫すると食べやすくなります。
煮込み料理やスープに使えば柔らかくなり
味もしみ込みやすいのでおすすめです。
逆に生のままサラダで食べると
食感が気になることがあるかもしれません。
注意したいのは
白さだけでなく黒ずみやカビ
強い異臭がある場合です。
この場合は劣化している可能性があるので
食べるのは避けましょう。
つまり「真ん中が白い=食べられない」ということではなく
見た目と匂いで判断し
状態に合わせた料理で美味しくいただくことができます。
真ん中が白いにんじんは食べられる?
見た目と味の変化
にんじんの真ん中が白くなると
まず目につくのは色の違いです。
鮮やかなオレンジ色が期待される中で
白い部分が現れると
「鮮度が落ちているのでは?」と不安になる方もいるでしょう。
ですが、実際には
成長や保存の過程で自然に起こる変化であり
必ずしも品質が悪いわけではありません。
見た目以外で感じられるのは食感と味の違いです。
白い部分はオレンジ色の部分に比べて繊維質が多いため
やや硬く感じることが多いです。
また、糖分が十分に蓄えられていないことから
甘みが少なく淡白な味わいになります。
そのため、サラダや生食では少し物足りなさを感じるかもしれません。
しかし、煮物やスープにすると繊維が柔らかくなり
味もしみ込みやすいので違和感なく食べられます。
つまり、白いにんじんは
「見た目と食感に違いはあるが、調理次第で十分美味しく食べられる」
という特徴を持っているのです。
栄養価は落ちるのか?
真ん中が白くなったにんじんは
見た目や味だけでなく
「栄養はちゃんとあるの?」と気になる方も多いと思います。
にんじんの代表的な栄養といえば、β-カロテンです。
これはオレンジ色の色素に多く含まれるため
白くなった部分にはβ-カロテンが少なくなっています。
そのため、白い部分はオレンジ色の部分に比べると
栄養価が低い傾向があります。
ただし、だからといって全体の栄養が
大きく損なわれているわけではありません。
白い部分が中心にあっても
周りのオレンジ部分には
しっかりと栄養が残っています。
さらに、にんじんには
食物繊維やカリウム、ビタミンCなども含まれているので
バランスよく食べれば健康への効果は十分期待できます。
つまり、中心が白いからといって
栄養がゼロになるわけではなく
むしろ他の野菜と組み合わせることで
効率よく栄養をとることができます。
調理法を工夫して全体を無駄なく使うのがおすすめです。
調理で美味しく食べられる工夫
白い部分が気になるときでも
調理の仕方次第で美味しくいただけます。
例えば煮物にすると
白い部分の硬さが和らぎ
味も染みやすくなります。
筑前煮や豚汁のような料理では
全く違和感なく食べられるでしょう。
また、スープやシチューなど
長時間煮込む料理もおすすめです。
逆に生食にする場合は
白い部分を薄切りや千切りにすると
食感が気になりにくくなります。
さらに、すりおろして
ドレッシングやスムージーに混ぜれば
色の違いも目立たず、栄養も摂れます。
炒め物に使う場合は、少し油を多めに使うことで
甘みが引き出され、硬さも気になりにくくなります。
白い部分は彩りがやや弱いため
パプリカやブロッコリーなど
カラフルな野菜と一緒に調理すると
見た目も華やかになります。
工夫次第で「少し残念に見えるにんじん」も
立派な食材に変わるのです。
注意した方がいい状態(カビや腐敗)
真ん中が白いにんじんは
多くの場合問題なく食べられますが
中には注意が必要な状態もあります。
例えば、にんじん全体が柔らかくなり
表面が黒ずんでいる場合は鮮度が落ちています。
また、真ん中が白いだけでなく
変なにおいがする、ぬめりがある、といった場合は
腐敗が始まっている可能性が高いです。
特にカビが見える場合は、その部分を取り除いても
根本的に菌が広がっている可能性があるため
食べるのは避けた方がよいでしょう。
保存状態によっては
真ん中が乾燥しすぎて
スカスカになることもありますが
この場合は食べても害はありません。
ただし、味や食感が落ちているため
無理に生で食べるよりは
煮込み料理に使った方が良いです。
白いこと自体は問題ありませんが
色以外の劣化サインがある場合は
食べないという判断が必要です。
子どもに食べさせても大丈夫?
お子さんに食べさせるときに
「白いにんじんをあげても良いの?」と
心配になる親御さんも多いでしょう。
結論として、中心が白いにんじんは
自然な現象であることがほとんどなので
子どもに食べさせても問題ありません。
ただし、白い部分は硬めで繊維が強いため
離乳食や小さな子どもには少し工夫が必要です。
例えば、柔らかくなるまで煮込んで
ペースト状にしたり
すりおろしてスープやおかゆに混ぜると
安心して食べさせられます。
噛む力がしっかりしてきた幼児期以降なら
薄切りにして煮物に入れれば大丈夫です。
また、白い部分は甘みが弱いので
甘みを感じやすいオレンジ部分と一緒に調理すると
子どもも食べやすくなります。
重要なのは「食べられる状態かどうか」を見極めることです。
カビや腐敗のサインがなければ
問題なく調理できますので
工夫して取り入れるのがおすすめです。
にんじんの真ん中が白くならないための栽培ポイント
土の質と栽培環境
にんじんを育てるとき
真ん中が白くなる現象を防ぐには
まず「土づくり」が大切です。
にんじんは根菜なので
根がまっすぐ伸びやすい環境が必要です。
土が固すぎたり石が多かったりすると
根がうまく育たず、中心部に空洞ができたり
白っぽくなる原因になります。
そのため、栽培前には土を深く耕して
ふかふかにしておくことが重要です。
理想的なのは
砂壌土(さらさらとした砂と粘土がバランスよく混じった土)です。
砂壌土は、水はけがよく
かつ水分を保ちやすい性質を持っています。
加えて、直射日光が当たりすぎる場所より
適度に日当たりが良く風通しのいい環境が
育成に適しています。
にんじんは発芽が難しい野菜ともいわれますが
土が柔らかく環境が整っていれば
根がしっかり育ち、白くなるリスクを減らすことができます。
適切な水やりと肥料
にんじんが
真ん中から白くなってしまう原因のひとつが
「水分や栄養のバランス不足」です。
水やりが少なすぎると中心部が乾燥しやすくなり
スカスカで白っぽい状態になります。
逆に水を与えすぎても根が割れてしまい
中心が変色しやすくなります。
そのため、土の表面が乾いたら
しっかり水を与える程度がちょうどよいバランスです。
肥料についても注意が必要です。
窒素肥料を多く与えると葉ばかり茂って
根が十分に育たず、中心が白くなる傾向があります。
肥料はリン酸やカリウムを
バランスよく含んだものを与えると
根の発育が良くなります。
特に追肥は控えめにし、根が太り始める時期に
過剰に与えないよう注意しましょう。
水と肥料の管理を適切に行うことは
中心部が白くなるのを防ぎ
甘くて美味しいにんじんを育てるための基本といえます。
種の選び方と品種の特徴
にんじんの中心が白くなるのは
栽培条件だけでなく「品種の特性」による影響も大きいです。
西洋系の品種(五寸にんじんなど)は
鮮やかなオレンジ色で中心までしっかり色づきやすく
白くなるリスクは比較的少なめです。
一方、東洋系や在来種は
中心部が薄い色になる傾向があり
家庭菜園で育てると「白っぽいにんじん」になりやすいのです。
そのため、中心まで
しっかりオレンジ色に育てたい場合は
「カラーにんじん」や「改良品種」など
色が安定している種を選ぶとよいでしょう。
さらに、種まきの時期も重要です。
高温期に育てると成長が早まりすぎ
中心が空洞になりやすいため
春や秋などの涼しい時期に種をまくと安定して育ちます。
つまり、品種の特徴と気候のタイミングを意識すれば
「真ん中が白いにんじん」を避けやすくなるのです。
間引きや収穫のタイミング
にんじん栽培では
「間引き」と「収穫時期」を間違えると
中心が白くなる原因になります。
種をまいた後、そのままにしておくと
株同士が混み合って栄養が行き渡らなくなり
根が十分に育ちません。
その結果、真ん中が白いにんじんになってしまうのです。
これを防ぐには、発芽後に数回間引きを行い
株間を3〜5cm程度確保することが大切です。
そうすることで1本1本のにんじんに
十分な栄養と水分が行き届きます。
収穫時期も大事なポイントです。
収穫を遅らせすぎると根が成長しすぎて
「す入り」しやすくなり、中心が白くスカスカになります。
品種ごとに決められた日数
(一般的には播種後100〜120日程度)を
目安に収穫するのが最適です。
つまり、間引きと収穫の管理をしっかり行うことで
色鮮やかで美味しいにんじんを育てることができるのです。
家庭菜園での予防策
家庭菜園でにんじんを育てると
どうしても「真ん中が白い」ものが出やすくなります。
しかし、いくつかの予防策を意識すれば防げます。
まず、土づくりは徹底的に行いましょう。
深く耕して石や固い塊を取り除き
ふかふかの土を用意します。
さらに、発芽が難しいにんじんには
「すじまき」や「点まき」で均等に種をまくと
後の間引きがしやすくなります。
水やりは土が乾かないように注意しつつも
与えすぎないことがポイントです。
また、栽培中に葉が青々と茂りすぎた場合は
肥料の窒素過多が疑われるので
追肥は控えるとよいでしょう。
収穫時期を逃さず
品種に合った日数で抜き取ることも大切です。
さらに、初心者は「改良品種」や「ミニにんじん」など
育てやすく色の安定した品種を選ぶのもおすすめです。
これらの工夫をすれば
家庭菜園でも
オレンジ色がしっかりしたにんじんを
収穫できる可能性が高まります。
買ってきたにんじんの真ん中が白かったら?
新鮮なにんじんの見分け方
スーパーでにんじんを買うとき
真ん中が白くなっているかどうかは
切ってみないと分からないのが難しいところです。
しかし、外見からある程度「新鮮さ」を
見分けるコツはあります。
まず注目したいのは表面の色つやです。
新鮮なにんじんは全体が鮮やかなオレンジ色で
しっとりとした質感があります。
逆に表面が乾燥して
白っぽい粉を吹いているように見える場合は
水分が抜けて鮮度が落ち始めています。
また、ヘタの部分(葉がついていた切り口)が
黒ずんでいないか確認するのも大切です。
黒ずんでいたり
柔らかくなっているにんじんは
鮮度が低下しているサインです。
さらに、手に取ってみて重みがあるものは
水分を多く含んでいて新鮮な証拠です。
軽くてスカスカした感触があるものは
中が空洞になっている可能性があります。
真ん中が白いかどうかは見ただけでは分かりませんが
「色つや・ヘタの状態・重み」をチェックすれば
失敗を減らすことができます。
保存方法で防げる白化現象
買ってきたにんじんをそのまま冷蔵庫に入れておくと
保存中に中心が白くなってしまうことがあります。
これは乾燥によって水分が抜けることが原因です。
にんじんは収穫後も呼吸を続けており
時間とともに内部の水分を失います。
そのため、保存方法を工夫することが重要です。
おすすめは、新聞紙やキッチンペーパーで包み
その上からポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れる方法です。
こうすると水分の蒸発を防ぎ、長持ちします。
また、葉付きのにんじんを購入した場合は
葉をそのままにしておくと葉に水分が奪われ
根の部分(食べる部分)が早くスカスカになります。
必ず葉は切り落として保存するようにしましょう。
さらに、湿度が低い冷蔵庫では
タッパーに水を少量入れて
にんじんを立てて保存する「水保存」も効果的です。
これにより白化現象を防ぎ
中心がしっかりした鮮やかなにんじんを長く楽しめます。
冷蔵庫での保管のコツ
冷蔵庫でにんじんを保管する際には
「乾燥対策」と「温度管理」がポイントです。
まず、にんじんは乾燥に弱いため
裸のまま冷蔵庫に入れてしまうと
すぐに水分が抜け、中心が白くなりやすくなります。
そこで新聞紙やペーパータオルで包み
さらに密閉袋に入れて保存するとよいでしょう。
特にジッパー付きの保存袋を使うと
湿度を保ちやすく、長持ちします。
また、冷蔵庫の野菜室は
通常の冷蔵室より温度が少し高めで
野菜に適した環境になっているので
必ず野菜室を使うのがコツです。
にんじんは低温に強い野菜ですが
0℃前後の極端な低温で長期間保存すると
内部がスカスカになることがあります。
そのため、2〜5℃程度の安定した温度で
保存するのが理想です。
さらに、長期間保存する場合は冷凍保存も可能です。
皮をむいて短冊切りやいちょう切りにし
軽く下ゆでしてから冷凍すれば
白化や劣化を防ぎつつ必要なときにすぐ使えて便利です。
白くなった部分を使う調理法
もし買ってきたにんじんを切ってみて
真ん中が白くなっていたとしても
工夫次第で美味しく食べることができます。
白い部分は繊維が多く少し硬いので
その特徴を活かす料理がおすすめです。
例えば
煮物やシチューに入れると柔らかくなり
味もしみ込むので食感が気になりにくくなります。
また、炒め物にすると香ばしさが加わり
繊維質の食感も心地よく楽しめます。
生で食べたい場合は
千切りやすりおろしにすると違和感が減りますよ。
さらに、スープやポタージュにして
ミキサーにかければ色のムラも目立たず
栄養も逃しません。
白い部分は甘みが弱いので
砂糖やみりんを少し加える料理と相性が良いです。
例えばきんぴらや甘辛炒めに使うと
調味料の旨みが加わってバランスが良くなります。
白化したにんじんは
「味が薄い分、他の食材や調味料を引き立てる」
食材として活用できるのです。
白いにんじんを避ける買い方のポイント
「できれば白くなったにんじんを買いたくない」
という方のために、選び方のコツを紹介します。
まず、新鮮さを見極めることが大前提です。
ヘタの部分が黒ずんでいないか
全体にハリがあるか、手に取って重みがあるかを
確認しましょう。
さらに、細すぎるにんじんは
中心部分が発達していないことが多く
白くなりやすい傾向があります。
ある程度太さがあり
均等に育っているにんじんを選ぶと安心です。
また、時期によっても白化しやすさは変わります。
特に夏に出回るにんじんは成長が早いため
中心が白くなりやすいです。
秋冬に収穫されたものは糖分が増して
色づきも良いのでおすすめです。
さらに、スーパーによっては
「地元農家の朝採りにんじん」など
新鮮なものが売られているコーナーがあります。
こうしたものを選ぶと
白いにんじんに当たる確率を下げられるでしょう。
白くなったにんじんを美味しく食べるレシピ
煮物で柔らかくして食べる
白くなったにんじんは繊維が多く
少し硬く感じることがあります。
そんなときは煮物に使うのが一番おすすめです。
煮物は時間をかけて火を通すため
白くて硬い部分も柔らかくなり
他の具材や出汁の味をしっかり吸って
美味しく食べられます。
例えば定番の筑前煮や肉じゃがに加えると
にんじん特有の甘さが控えめな分
全体の味がしつこくならずバランスよく仕上がります。
また、豚汁やけんちん汁に入れても
食感が柔らかくなり、食べやすさが増します。
白いにんじんは彩りがやや弱いのですが
こんにゃくやしいたけなどの具材と合わせると
見た目も地味になりすぎず
和食らしい温かみを感じられます。
さらに、煮物の味付けを濃いめにすると
白化したにんじんの風味の薄さを補えるため
満足度の高い仕上がりになります。
硬さが気になる場合は
乱切りよりも薄切りやいちょう切りにして加えると
煮えやすく食感も滑らかになります。
炒め物で香ばしさを出す
炒め物も白くなったにんじんを活かすのに適した調理法です。
油で加熱すると甘みが引き出され
香ばしさが加わることで淡白な味わいが補われます。
例えば、豚肉や鶏肉と一緒に炒めると
肉の旨みと油分がしっかり絡み
白い部分も違和感なく楽しめます。
中華風にオイスターソースや醤油で味付けすれば
彩りは控えめでも風味豊かなおかずになります。
また、きんぴらにんじんにして甘辛いタレで炒めると
硬さが気にならなくなり
ご飯のおかずやお弁当にもぴったりです。
さらに、カレー風味やガーリック風味で炒めると
大人から子どもまで食べやすくなります。
炒める際は油をやや多めに使うのがコツで
パサつきを抑えてしっとりと仕上がります。
白い部分は彩りに欠けるため
ピーマンやパプリカなどカラフルな野菜と組み合わせると
見た目も鮮やかになり、食欲をそそる一品になります。
スープやポタージュにする
白くなったにんじんを最も美味しく活用できるのが
スープやポタージュです。
にんじんは煮込むと繊維が柔らかくなり
甘みも引き出されるので
白い部分の特徴が気にならなくなります。
例えば、コンソメスープに薄切りで入れると
他の野菜や出汁の旨みを吸って美味しく仕上がります。
さらにおすすめなのはポタージュです。
にんじんと玉ねぎ、じゃがいもなどを一緒に煮込み
ミキサーにかければなめらかなスープになります。
白い部分は色が薄いので
全体のオレンジ色が少し控えめになりますが
牛乳や生クリームを加えると
逆にまろやかで優しい色合いに仕上がります。
また、冷製スープにすれば夏でも飲みやすく
栄養補給にもぴったりです。
白化したにんじんは甘さが控えめなため
バターや塩でしっかり味付けすると
コクが増して美味しくなります。
スープやポタージュは
「味も色もごまかしやすい」調理法なので
白いにんじんを気にせず使える万能な活用方法といえるでしょう。
すりおろしてサラダやドレッシングに
白くなったにんじんを生で食べたいときは
すりおろしてサラダやドレッシングに使うのが
おすすめです。
そのまま輪切りやスティックで食べると
硬さや甘みの薄さが気になりますが
すりおろせば食感が滑らかになり
ドレッシングや調味料と混ざって
美味しくいただけます。
例えば、すりおろしたにんじんを
ポン酢やオリーブオイルと合わせれば
爽やかなサラダドレッシングになりますし
マヨネーズと混ぜれば子どもでも食べやすい味になります。
キャベツやレタスのサラダに加えると
彩りが増し、食感にも変化が出ます。
また、にんじんラペ(細切りサラダ)にする場合も
白い部分を多めに使うと食べやすくなります。
さらに、すりおろしたにんじんを
ヨーグルトやジュースに混ぜれば
簡単なスムージーとしても活用できます。
白化したにんじんは
生食ではやや物足りなさを感じますが
調味料と合わせることで
「爽やかな脇役」として活躍できるのです。
漬物やピクルスにして楽しむ
白くなったにんじんを
保存しながら美味しく食べたいなら
漬物やピクルスにするのもおすすめです。
酢や塩に漬けることで硬さがやわらぎ
味が染み込んで食べやすくなります。
例えば、甘酢にんじんのピクルスは
彩りが少し控えめでも味はしっかりしており
食卓の箸休めにぴったりです。
白い部分は酸味と相性がよく
マリネにしても美味しく食べられます。
また、ぬか漬けにすると独特の風味が加わり
繊維質の食感も楽しめます。
作っておけば冷蔵庫で1週間ほど持ちますよ。
特に夏場はさっぱりと食べられる
ピクルスが向いていますし
冬には塩麹やしょうゆ麹に漬けると
深い旨みが楽しめます。
白くなったにんじんを
「漬ける」という方法で活用すれば
見た目の不満を解消しながら
むしろ味わいをプラスできるのです。
まとめ
にんじんを切ったときに真ん中が白いと
「古いのかな?」「食べても大丈夫?」と
心配になることがあります。
しかし、その原因は主に
成長過程のスピードや水分・栄養の偏り
品種の特徴、保存状態などであり
自然に起こる現象です。
白い部分は繊維が多く硬めで
甘みが少ない傾向がありますが
基本的には問題なく食べられます。
煮物やスープ、ポタージュにすれば
柔らかくなり、美味しく活用できますよ。
さらに、栽培や保存の工夫によって白化を防ぐことも可能です。
家庭菜園で育てる場合は
土づくりや間引き、収穫のタイミングを意識し
購入時は鮮度の見極めを行えば
中心まで鮮やかなにんじんを手に入れることができます。
万が一真ん中が白かったとしても
調理方法を工夫すれば十分に美味しくいただけますので
捨てずに上手に活用するのがおすすめです。